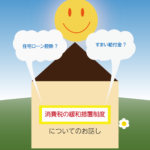◆家づくりのコラム:上り框について
日本の住宅の玄関で、重要な役割を果たしているのが上り框です。
「あがりがまち」と読み、靴を脱いで家の中に入る日本の玄関には欠かせない存在と言えます。
今回は、そんな上り框の意味や、使われる材料とその特徴についてお伝えします。
上り框は、住まいを訪れた誰もが目にする部分になり、家の印象を左右する部分とも言えますので、その役割や材料の特徴をよく理解した上で計画したいですね。

上り框とは
上り框とは、玄関から廊下やホールに上がる段差に、床材の端部を隠すように水平に取り付ける横木のことです。
玄関で必ず目に入る場所に設置されますので、見栄えがいいことが求められます。
また、出入りの際にはまたいだり、踏んだり、腰掛けたりする部分ですので、耐久性が必要になります。
直線の框はもちろんですが、曲線を描く形状の上り框も人気で、来客を優しく迎えることや玄関のスペースの有効活用にも役立ちます。
それぞれの住まいに合った形状や素材で上り框を選びたいですね。
上り框の高さ
上り框は、外と室内を分ける意味や、水や外の汚れが室内に進入しにくくすること、靴を脱いだり履いたりする際に動作がしやすい高さの設定をする必要があります。
一般的に上り框の高さ設定は200mm程度とされています。
これは階段1段分と同じくらいの高さです。
健康な成人が上がりやすい高さですね。
この高さ設定は、様々な工夫ができる部分でもあります。
一般的な200mmを上るのが辛い小さい子どもやお年寄りが生活する住まいの場合、手すりや式台や靴脱ぎ石と組み合わせることで高さを緩和することもできますが、框の高さを低くすることも検討できます。
車イスの乗り入れも視野に入れて、全く高さの無い玄関を想定することもできますね。
家族の状況を考慮して、バリアフリー化する必要があればぜひ検討したい部分です。

段差を極力少なくして将来的にも安心な設計です♪
逆に、高さを400mm以上にすることで、腰掛けやすいベンチとして利用することもできます。
来客が多い場合、腰掛けて話しをする場所や、ガーデニング等のアウトドアの趣味がある場合は休憩場所としても便利に使えます。

少し高さを持たせて腰掛けにもピッタリです!
家族の状況や住まい方、玄関の使い方に合わせて上り框の高さを設定すると、より暮らしに寄り添った便利な住まいになります。
上り框に使われる素材
上り框の素材は耐久性のあるものはもちろんですが、玄関の個性を演出する役割もありますので、住まいの雰囲気に合った材質を選びたいですね。
一般的に上り框に使われる素材は以下のようになっています。
-
木材
無垢材や集成材や既製品など木材の玄関框は、樹種もカラーバリエーションも豊富なため、空間のコーディネートがしやすく、価格帯も低く設定されているため、最も人気な選択肢です。
特殊な加工で曲線形状の上り框を作ることも可能です。

-
石材
天然の石材は高級感があり、玄関の空間演出で活躍してくれる素材です。
大理石や御影石などインテリアに馴染みやすく、床材として使われることの多い石材がよく使われます。

-
タイル
耐久性が高く、汚れに強いタイルは上り框に適した素材です。
床材がタイルの場合、タイルを上り框や玄関巾木にすることで統一感のある空間になります。
-
ステンレス
ステンレスの上り框は、車イスの乗り入れなどの傷が気になる玄関の框として人気の素材です。
また、公共施設等の上り框にもよく使われているほど、高い耐久性を期待できる素材です。
インテリアや、玄関框に求める耐久性や、予算にあわせて適した素材を選びたいですね。
玄関の上り框の役割と、高さの検討、素材についてお伝えしました。
玄関は毎日使うもので、家の顔とも言える部分です。
住まい全体の雰囲気が良くなるような、それぞれの家庭に合った上り框の計画ができるといいですね。
◆ 執筆者プロフィール ◆

ー 佐藤結伽 ー
2級建築士。
2人娘の育児にも奮闘中。
最近、自邸の建設をし
注文住宅を購入する事の素晴らしさと、大変さを身をもって経験した。
関連記事
◆家づくりのコラム:パントリーについて
イマドキの家づくりやリフォームで人気のパントリー。 便利に活用できる計画をすれば、キッチンだけではなく、住まいをすっきりさせ、効率的に家事が行えるようになります。 今回は、そもそ […]
- 作成者: k-juken
- カテゴリー: 家づくりのコラム
- タグ: ウォークインパントリー, ウォークスルーパントリー, パントリー, 食品庫